|
Angling Net / Topwater Bass Fishing 川のバスを釣ること 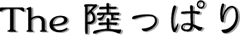 
川でバスを釣ることを「リヴァーバシング」というらしい。今でこそ川バスは常識になっているけれど、バス釣りが日本に入ってきたころは、ノーザンラージマウスバスは止水の魚であると紹介されていた。 流水はスモールマウス、止水はラージマウスで棲み分けてるというのがもっぱらの机上の知識だった。 したがって、リヴァーバシングという言葉などなかった。川でラージマウスバスを釣るという認識はまったくなかったのだ。 あるとき(もう二十年以上も前のこと)兵庫県のT湖に注ぐ幅10mほどの川で、何百匹という魚が川を溯るのを見た。ウグイかなと思い、試しにラパラを投げてみたら機銃掃射のような連続ヒット。なんとこれがすべて30cm以上のバスの成魚だった。 早朝から昼近くまでやってもまったく釣れなかったバスが、こんな場所で連続ヒットとは‥‥‥。「バスは止水の魚ではなかったのか?」という疑問が渦巻く。  そんなことがあって以来、その気になって川を釣り歩いた。すると意外にも、川にはバスが大量に棲息してることがわかった。しかも、やたら太い(体高が高い)。強い流れに耐えているうちに骨格や筋肉が発達したのだろう。
そんなことがあって以来、その気になって川を釣り歩いた。すると意外にも、川にはバスが大量に棲息してることがわかった。しかも、やたら太い(体高が高い)。強い流れに耐えているうちに骨格や筋肉が発達したのだろう。川バスは、止水のバスより魚食性が強い。なにしろ川にはおびただしい数の小魚が泳いでいる。オイカワ、カワムツ、アユ、ウグイ。当然、それらのミノーを餌にして大きくなる。つまり、ミノーシェイプのルアーにより反応するということである。 したがって、川でバスを釣るにはミノープラグを使うのが合理的で手っ取り早い。いわゆるマッチザベイトだ。しかし、トップ屋はそうはいかない。それでは楽しみが少なすぎると考える。無理してでもトップで釣りたい。 例えばザラスプークのような細長いペンシルベイト。あるいはダイイングフラッター、デビルズホース、チャグバグなど、細長いものならベイトフィッシュに見えるのではないかと手当たり次第投げてみた。 最も効果的だったのは、フローティングミノーのリップを折って、フックにヘラブナ用のヒューズシンカーを巻き付けてバランスをとったもの。威力は絶大だった。当時は今のようなリアルミノーペンシルは存在しなかった。 そこで‥‥‥自分でバルサを削って細身のミノーペンシルを作ってみた。  アルミ箔を貼ってより小魚に見えるようにした。
アルミ箔を貼ってより小魚に見えるようにした。重要なことは垂直浮きにすること。これで釣れ方がグンと変わる。 流れのど真ん中にぶち込んでも、垂直立ちのペンシルは流れの影響を受けにくい。ポーズを取る時間が稼げる上に動かし始めが楽になる。 こういうタイプのミノペンが川バスに効く 左からRed-Pepper, Sammy, Inukami, Recent そうするうちに、川でバスを釣ることは常識になっていった。釣り人は口々に「川バスは太い」「川バスは止水の二倍引く」などと言いはじめた。遅かれ早かれ、みな同じことをやっているのだ。 川のバスには、止水のそれにない魅力がある。流れの変化を読むことは、川の釣りすべてに共通するテクニックだ。むずかしいがマスターすると面白い。釣ったときの達成感も大きい。今後ますます川のバス釣りは研究されるだろう。しかし‥‥‥ 川の釣りには問題が多い。 そもそも漁業権魚種でないバスを河川の漁協が認めないという問題がある。もちろん遊漁証を買う。「雑魚釣り券」という遊漁証だ。これがないと川で釣りをしてはいけないことになっている。 で、建前ではウグイやニゴイ、ナマズなどの雑魚を釣ることになる。つまりバスは「釣れない」のである。もし間違って釣れてしまったら「殺せ」という。再放流してはいけないという。バスは日本の川では概ねそういう魚種になっている。 もちろん、漁協に従うか従わないかは釣り人の良心である。しかし良心とは果たして「良い心」なのか‥‥‥? 26/Augast/2001 Ikasas Ikuy  Return to Topwater Bassin' Return to Topwater Bassin' |